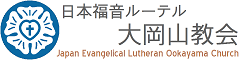天国での関係
ルカによる福音書 20: 27 – 38
今年は教会員で亡くなられた方が6名おられます。それ以外にもご家族を亡くされた方が複数いらっしゃいます。大変多くの方が天に召されました。私たちはお葬儀の際に亡くなられた方に向かって「天国でまた会いましょう」と声を掛けます。それはとても自然に出る言葉で、その言葉に偽りはありません。私はいいことだと思います。
私達がイメージしたり考えることの多くは、それまでの経験の中で実際に触れたり、書物で読んだり、聞いたりしたことが元になっています。ですから今日福音書の日課になっている死んだあとの事柄についても、私たちは生きている世界の延長線上で考えようとするのです。たとえば、愛する人が亡くなったとすると、自分が死んだ後に天国で再会すると考えます。その再会の仕方は、今と同じ姿で、同じ出会いの仕方でイメージしています。そしてそれを復活と結びつけて考えています。それは愛する人を失った悲しみを癒すためにも大きな力になります。しかし今日の福音書は、厳密な意味でそのような復活のイメージを覆すものです。
サドカイ派の人々がイエスさまに質問をしている箇所です。サドカイ派というのは、ユダヤ教のグループの一つで、モーセの律法のみに重きを置いている人たちです。比較的保守的で裕福な人たちが多かったそうです。同じユダヤ教のグループには、ご存知のファリサイ派があります。彼らは同じように律法に熱心なグループだったのですが、彼らはモーセの律法だけでなく、むしろ預言者や文学書、さらにはモーセの言い伝えとされる口伝伝承の言葉を大変大切にしていました。ここでの議論は、復活についてです。モーセの律法には「復活」ということが出てきませんので、サドカイ派の人々は復活を信じていませんでした。しかし、ダニエル書やモーセの口伝伝承には復活を示唆する言葉が書かれていましたので、ファリサイ派の人々はこれを信じていたのです。
そこでサドカイ派の人は、モーセの律法、申命記25章5節~10節を下敷きにしたたとえをもってイエスさまに質問します。それは質問というよりも、嘲笑を込めた挑戦であったと思います。なぜなら彼らはイエスさまの答えによって自分たちの考えを変えようなどとは端から思っていなかったからです。「ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎをもうけねばならない」。これは家の後継者を残すために定められた律法で、「レビラート婚」と呼ばれているものです。結婚は跡継ぎを残すための一番の目的と考えられていました。従って、子どもを産むことができない女性はみじめな立場に立たされていたのです。
この兄弟が子どもを残さずに亡くなった場合、その弟が兄の妻の夫になるということは日本でも先の戦争まで時々行なわれていたと聞きます。そこで彼らは言います。「ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女はだれの妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。」彼らの考えは、今生きているこの世の生活に根ざしていました。裕福で社会的な地位の高かった人たちが多かったので、それを守ることが大切だったのかもしれません。彼らがここで想定している復活は現世の延長でした。ですから、復活があるとするのならば、モーセの律法に照らすととんでもないことになりますよ、というのが彼らの主張なのです。実は、復活を主張していたファリサイ派の人の復活観も、この世の延長としての復活でした。ですから、中には復活後の女性は毎日でも出産することができるという人もいたほどでした。これに対してイエスさまの考えておられる復活はそうではありません。復活は終わりの時の復活です。それは現世の延長でもなく、現世への逆戻りでもなく、神様の新しい世界への誕生であり、神様との完全な関係への扉なのです。
復活のイエスさまの姿を思い出してください。「私の手や足を見なさい。まさしく私なのだ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見えるとおり、私にはそれがある」と言い、さらに焼いた魚をむしゃむしゃと食べて見せられました。しかし、その一方で、締め切った部屋に突然現れたり弟子たちの間から忽然と姿が見えなくなったりしているのです。復活のイエスさまの姿は、私たちの考えを超えたものです。このように復活は、存在の様態、姿かたちで捉えられるものではありません。現世の延長ではなく、神様の世界での出来事なのです。そして復活する人は、その神様の出来事に与るのです。つまり私たちが死んで復活した後は、天使に等しい神の子として生きるのです。
さらに、イエスさまは言われます。「この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁ぐこともない。この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等しい者であり、復活にあずかる者として、神の子だからである。」当時の結婚観は今のように多様ではありませんでした。人が結婚を必要とするのは、死があるからです。死があるからこそ結婚をして子孫を残し、死を乗り越えようと考えたのです。しかし復活した人には、もはや死はありません。その意味で復活した人には結婚の必要がなく、その存在も生前の夫婦関係、親子関係、友人関係の中で生きるのではなく、まったく新しい姿で、天使に等しい存在なのです。天使にあるのは神様との関係だけなのです。
イエスさまは続けられます。「死者が復活することは、モーセも『柴』の個所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は、神によって生きているからである。」イエスさまの考えでは、アブラハムもイサクもヤコブも、死に留まるのではなく復活するのです。ですから、神様も死にとどまる人の神ではなく復活する人の神であり、人を生かす神なのです。
神様は人を生かすために、命の主を私たちに送られました。イエスさまは言われます。「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬことはない。」
神様は復活を私たちにも与えられます。私たちは死を終わりとして恐れるのではなく、復活を信じることによって、神様の新しい世界での希望の先取りが許されているのです。それはただイエス・キリストを通して、今を生きるわたしたちにも与えられる希望なのです。そして神様は私たちがこの希望を持つことによって、今を本当に生きたものになるようにしてくださるのです。