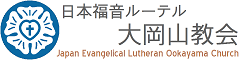開放の恵みを共に喜ぶ
イザヤ書 58: 9b – 14、ヘブライ人への手紙 12: 18 -29、ルカによる福音書 13: 10 – 17
先日、風邪をひき、どうにも体調が悪くて、主日礼拝を欠席しました。当日の朝、役員の皆さんに連絡メールを書く際、「礼拝を休みます」と書きかけ、しばらく考えて「礼拝を欠席します」と書き直しました。「休む」から「休息」という言葉が連想され、礼拝に行くことこそ本来の休息なのではないか、礼拝を休むという表現は礼拝が自分の務めであり、務めを休むと言っているようなものではないか、と痛む頭で考えたのです。
本日の福音書箇所には、「安息日に、腰の曲がった婦人をいやす」というタイトルがつけられています。安息日を表すヘブライ語の「シャバット」は、「休む」「止める」という意味の言葉だそうです。出エジプト記には「安息日を心に留め、これを聖別せよ。「七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事をしてはならない。」という十戒の教えが書かれており、申命記でモーセがイスラエルの人々に対して十戒を伝える場面では、安息日に仕事をしてはならないのは、エジプトの国で奴隷だった自分たちを神様が導き出し、奴隷状態から解放してくださったことを思い起こすためだと説明されています。
また、イザヤ書 58章13節~14節には、「安息日に歩き回ることをやめ/私の聖なる日にしたい事をするのをやめ/安息日を喜びの日と呼び/主の聖日を尊ぶべき日と呼び/これを尊び、旅をするのをやめ/したいことをし続けず/取り引きを慎むなら/そのとき、あなたは主を喜びとする。」とあります。
週のうち 6 日間は、生活する上で必要なこと、稼ぎを得るための労働、仕事を優先していても、生活全般のことでいろいろな心配事があったとしても、安息日だけはそれを中断して礼拝堂に集まり心と時間を神様に向ける、神様が自分たちを解放してくださったことに感謝する、それが安息日を守る目的です。さまざまな束縛から解放されて、人も、動物までも神様と共にあって安息し、喜ぶのが安息日です。
安息日の掟は、ユダヤ人にとって非常に重要なものでした。安息日を守ることが、ユダヤ人が神の民であるというアイデンティティを支えてきたとも言われています。
ところが、時代を経るにしたがって、数々の細かい規定が付け加えられ、それらの規則をすべて守らなければ神様の意思に背くことになると考えられるようになったため、イエス様の時代には、安息日が逆に人々を縛るものになってしまっていました。安息日に病気をいやしてはいけないという規定もその一つです。
安息日に病人をいやされるイエス様は、その矛盾を指摘されるのです。その日会堂で教えておられたイエス様は、病によって 18 年間も腰が曲がったまま伸ばすことができないでいる女性に目を留められます。
この女性は、脊椎の周りの腱やじん帯に炎症がおこり、徐々に硬直していく進行性の病気を患っていたと考えられているようです。18 年前に自分は何をしていただろうと思い起こし、その頃から 18 年もの間、腰が曲がったままだったらと考えると、そこには絶望しか見いだせません。病気が進行していく不安と不自由さ、痛み、苦しみに心がつぶれそうになります。
当時の人々は、病気や障害を神様の裁きと関連付けて考えていましたから、この女性は病気から生じる苦しみ、痛みに加え、人々の偏見に苦しみ、社会の交わりに入れない孤独にも耐え続けてきたに違いありません。
イエス様は、この女性を近くに呼び寄せ、「婦人よ、病気は治った」と言われました。原文に忠実に訳すと、このときのイエス様の言葉は、「あなたの病気から解かれた」となるそうです。
この女性は病気によって、長い間、安息日の喜びに与ることができずにいました。聖書には「病の霊に取りつかれている」「サタンに縛られていた」と書かれていますが、これは自らの意思に反して、神様の御心にかなう働きができない状態を指す言葉です。病気を患ったことによって、彼女は、その症状以上のものに縛られていたのです。
イエス様は、安息日こそ縛られた状態から解放するのにふさわしいと言われます。社会に軽んじられ、価値がないと考えられ、その痛みに目を向けられることもないような存在が神様との関係を回復し、神様を賛美することこそ、安息日の趣旨だからです。
イエス様の言葉は、そこで終わりません。ルカ 13:18 には「そこで、イエスは言われた。『神の国は何に似ているか。』」と書かれています。「そこで」と訳されている箇所は、英語の聖書では、「だから」や「それゆえに」という意味の言葉が使われています。18 年間病気に苦しめられた女性がその病から解放されることが安息日に相応しいことから、神の国がからし種やパン種にたとえられるのです。小さく価値がないと思われるものが大きな働きをしうるのが神の国です。
会堂長は、安息日以外の日に来て治してもらえばよい、と主張しました。18 年間続いた女性の苦しみに思いを寄せることはありませんでした。しかし、イエス様の目には、この女性が「アブラハムの娘」、神の民の大切な一員として映っていました。
イエス様は「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。」(マタイ 11:28)と言われます。あの日、女性が身体の痛みをおして会堂に来たことをイエス様は見逃しませんでした。女性が声を上げることなく、その場にいたことに気づかれました。
キリスト教会では安息日を守ることはしません。代わりに主の日に礼拝を守ります。
趣旨や形は変わりましたが、私たちが日常の働きの手を止め、神様の前に集まって神様から休息をいただくことに変わりはありません。礼拝は、私たちがどんなに小
さな存在であっても、価値あるものとして目を向けてくださるイエス様の声を聞き、自分たちを神様から遠ざけている重荷から解放されていることを喜ぶ時です。日常生活において、様々な思い煩い、他人への不満、何かの責任への重圧などに心を乱すことがあっても、将来への不安や体の不調、病気によって心を支配されている自分をリセットし、神様が喜ばれる生き方をしようという思いをいただいて、1 週間をスタートしたいと思います。
本日の派遣の賛美歌は、教会讃美歌の 349 番「主に仕えまつらん」を選びました。この讃美歌の英語の題は、I want to be a Christian.と言います。訳すと、「私はクリスチャンになりたい」という意味です。主に仕えまつらん、主を愛しまつらん、と歌う歌詞の裏には、主が私に仕えてくださったから、主が私を愛してくださったからという言葉が隠されていると思います。イエス様が私たち一人一人に目をむけ、私たちを重荷から解放してくださっているから、私たちは、きよきものとならん、と歌い、イエスのごとくならん、と願うことができます。
ユダヤ人たちは、安息日によって自分たちが神の民であることを確認してきました。
私たちは、イエス様に仕えられ、イエス様に愛されることによって、キリスト者としての歩みへと導かれるのです。