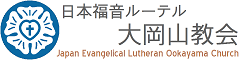腰に帯を締めて
創世記 15: 1 – 6、ルカによる福音書 12: 32 – 40
『天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみるがよい。』これは神様がアブラハムに対する祝福の言葉、神様は跡を継ぐ子供のいない年老いたアブラハムに向かってあなたの子孫はこの空の星の数のように増えると言います。夜の明かりが明るい東京ではピンときませんが、海や山など大自然の中で見える思わず声が出るほど空に広がった『天の星』たちの数を思い起こせば、神様の祝福の大きさを想像できるでしょう。今日の第一の日課はイスラエル人の始祖として尊敬されているアブラハムの物語、その前半のクライマックスにあたる部分です。
創世記の主人公のひとり・アブラハムがイスラエル人の祖先と呼ばれているのは、彼が創世記の主人公たちの中の最も古い『イスラエル人』だからです。天地創造やアダムの物語、ヨナの洪水、バベルの塔は創世記ではアブラハムよりも前のこととして書かれていますが、アブラハム以降の物語とは違う世界観にあるようです。
対して、12 節以降はアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフと続く一族の歴史の物語が大きな河のようにつながっています。その中で①アブラハムの物語はその始まりであること、②神様がアブラハムとその子孫に特別な祝福を与えた、つまりイスラエルの民族への祝福が与えられ、イスラエルがイスラエルとして立つ唯一絶対の根拠が書かれていること。③アブラハム自身の強い信仰のこと。これがあってアブラハムはイスラエル人の始祖・祖先として尊敬されています。
アブラハムは信仰の父とも呼ばれています。彼はセムの族長としてカルデアのウル、現在のイラク・ユーフラテス川のほとりに生まれました。彼は 75 才で神様の召しを受け、約束の地を信じ求めて、同じく年老いた妻であるサラと共に旅立ちます。苦難の旅の中で、神様は後を継ぐ子供がいないアブラハムに向かって約束の地・カナンを見せ、『この広大な地を空の星のように増えるアブラハムとサラの子孫に永久に与える』と約束したのが今日の場面です。老齢のアブラハムは神様のこの言葉を信じました。
アブラハムは神様の約束に対してゆるぎない信仰を持っていました。この約束には神様の言葉だということを除けば信じる根拠は何もありません。約束が実現する何の兆候も見ていません。しかし、アブラハムは神様の言葉を信じます。このアブラハムの信仰=「信じる」ということは「全面的に受け入れる」ということでした。自分であれこれ考えることをやめ、神様に全て任せ、全てを受け入れることです。一見自我に欠け消極的な姿勢に見えるようなこの信仰、しかしアブラハムはこのような信仰の上に立つことによって、自分がどんな困難の中に置かれた時でも揺らがず立ち続けたのでした。
今日の福音書の言葉に『腰に帯を締め、…』という言葉があります。この『腰に帯を締める』のは、食事の給仕をする“しもべ”の姿です。主人のために懸命に働く姿勢と決意。この姿勢を保ったままで真夜中でも目を覚まし、主人の帰りを待ち続けなさいとイエス様は命じます。
しかしこの帰ってくる主人は意外な行動に出ます。帰って来るや否や待っていた“しもべ”たちのために帯を締め、かれらを食卓に着かせ、そばに来て食事の給仕をしてくれるのです。ここで“しもべ”たちはもちろん私たち人間、主人はイエス・キリストです。この天から来られるキリストは私たち人間に仕えるために来られるのです。私たちに仕えられるために来るのではありません。先月の大岡山教会講座では鷲見神学生から『礼拝は私たちが神に奉仕するのではなく、神が私たちに奉仕するのだ』というお話を聞きましたが、まさにそれと同様にイエス様は私たちに仕えてくださいます。これは十字架の死と復活に至るまで続きました。
『小さな群れよ、恐れるな。あなたがたの父は喜んで神の国をくださる。』このイエス様が約束される神の国とはアブラハムとの契約のようなこの世に限定されたものではありません。神のみこころが全てに及ぶ世界、つまり神様による揺らぐことのない真の平安とそこから生まれる尽きることのない永遠の希望が神の国の本質です。アブラハムの契約とは次元が違います。ではこの約束を信じるための根拠は?それは全ての人に寄り添い仕えた生涯、人の罪を贖う十字架、永遠の命を与える復活、これら全てのイエス・キリスト歩んだ跡が神の国の到来を示す証拠です。
『目を覚まして待ちなさい』とイエス様は言われます。私たちは腰に帯を締め、人に仕える者として歩みながら神の国を待ちます。この『待ちなさい』という言葉は油断して神の国を逃したらひどい目に合うという警告ではありません。素晴らしい神の国を神様は私たちに渡したくてしょうがない、それをぜひ逃さないでという勧めの言葉です。そんな神様の勧めを喜んで受け、従いたいと思います。