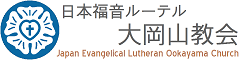しつこく何度でも
創世記 18:20~32、ルカによる福音書 11: 1~13
20 年ほど前、私は年に 3 回くらい仕事で中国に出張していました。会社の旅費を使って出張するので、1 回の出張で 1 か所しか回らないということはほとんど許されず、3 か所、4 か所のお客さんを回りました。ですから 1 回の出張は 1 週間を超えることが多かったです。ただ、1 か所の用事は半日程度で終わりますから、その日の仕事が終わった後や仕事のない土日は、買い物をしたり近所の観光をしたりしました。
中国の中部にある西安で午前中に仕事が終わり、午後の時間が空きました。そこで私は同行してくれている中国系の営業の人と、唐の時代の女帝である則天武后の墓に行こうということになりました。西安の市街地から 1 時間半ほどタクシーに乗って西に向かい、墓のふもとに着きました。皇帝の墓ですから、標高 1000m ほどの山全体が墓になっています。ふもとから片道 1 時間くらい登らないといけないところでした。登り始めて少しすると、小学校 5、6 年生くらいの女の子が私の横に付いて、干支を刺繍した壁掛けを見せてきました。どうやらお土産として私に買ってほしいということのようです。特に欲しいものでもなかったので、「いらないよ」と断りましたが、女の子はずっと私に付いてきて、目が合うたびに壁掛けを見せてきます。何度も「いらないよ」と言ってあきらめさせようとしましたが、1 時間くらいその女の子は私のそばを離れずに付いてきて、上り坂で疲れた体がさらにずっしり重くなったことを覚えています。
今日の福音書の日課は、主の祈りが読まれました。毎週の礼拝でも祈っていますので、皆さんもよくご存じの祈りです。式文では、もともと主の祈りは聖餐式の中で唱えられるものです。私たちの教会では、カトリックのように毎週聖餐式を行っていませんが、聖餐式のない礼拝(みことばの礼拝と呼ばれます)でも、派遣のパートの最初の部分で祈ります。訳文がカトリック= 聖公会共同訳のものを使うようになってしばらく経ちましたが、皆さんは慣れてきたでしょうか。このように主の祈りは毎週祈っていますが、それは主の祈りが私たちにとってそれだけ大切な祈りだということなのです。
私たちは洗礼を受ける前にルターが書いた小教理問答書をテキストとして牧師先生と勉強をします。その中では洗礼の意味とともに十戒、使徒信条、主の祈りの勉強をします。最近洗礼を受けた方はよく覚えているかと思いますが、皆さんも覚えているでしょうか。主の祈りについては洗礼を受けた方はすでに勉強をしていると思いますので、今日は主の祈りの言葉ひとつひとつについてはお話しません。
主の祈りを弟子たちに教えた後、イエス様は弟子たちに「しつように求めなさい」ということを教えられます。真夜中に突然友人が訪ねてきたが何も出すものがない。そこで近所の友達の家にパンを貸してほしいと頼みに行きます。当時、パンは一日に必要な分だけを焼いて食べるものでした。いきなりパンを貸してほしいと頼まれても、焼く手間がかかります。しかも真夜中で子どもも寝ています。いくら友達だからといって、すぐに出せないものを頼まれたら誰でも断ると思います。しかしイエス様は断られてもしつように頼みなさいと言われます。一度断られても、何度も何度も頼めばその望みはかなえられる、と言われます。人間同士だったら、真夜中に外で騒がれたら近所迷惑になってしまう、とか、頼みごとを聞かないことで逆恨みをされてしまうということを思って願いを叶えることもあるでしょう。しかしこの部分はイエス様がたとえとして話されている部分です。私たちが何度も願い事をする相手は人間に対してではなく神様に対してです。
神様は私たちが願えばそれをすべて願ったとおりになさるわけではありません。神様は私たちにとって一番良いと考えることをしてくださるだけです。願ったものをすべて実現するのであれば、それは願いではなく命令になってしまいます。それでもイエス様は私たちに「だれでも、求めるものは受け、探すものは見つけ、門をたたく者には開かれる」と言われます。しつように願えば、神様は心を動かしてくださると言われます。それはなぜでしょうか。
イエス様は弟子たちに、祈りの冒頭で神様の名前を呼ぶときは「父よ」と言いなさいと教えられました。イエス様は、神様は父、人間である私たちは子と言われます。親子の関係であれば、親としては最初ダメと思っていても、子どもが何度も願い事をすれば、心を動かして願いを叶えることがあります。子どもから見れば、親は最も信頼する人ですから、いつか願いを叶えてくれるかもしれないと希望を持ち続けることができるのです。親としても、子どもは最も愛する相手ですから、子どものためになるのであれば願いはかなえてやりたいと思います。神様は私たち一人ひとりを愛してくださっています。子どもである私たちは神様を信頼して付いていきたいと考えるのです。
今日読まれた第一の朗読は、先週読まれた箇所の続きの部分です。3 人の旅人としてアブラハムの前に現れた神様が、罪深い町であるソドムとゴモラを滅ぼすことについて語り合います。
アブラハムは、ソドムの町に正しい人が 50 人いたら町全体を滅ぼさずに赦してほしいと執り成します。神様はその願いを聞き入れます。ところがアブラハムは正しい人の人数を 50 人から 45 人、40 人、30 人、20 人、10 人まで減らしていきます。最初の 50 人から比べたら、正しい人の人数が 2 割になるまで条件を低くして、神様もそれを受け入れます。
説教の冒頭で、中国出張をしていたときのことをお話ししましたが、もう一つ思い出をお話しします。観光地は、どこでもそうですが露店でお土産を売っています。仕事がない週末に、私も上海で 1000 円くらいのお土産を買いました。ところが出張に同行してくれている営業の人に見せると、「露店では売っている値段で買ってはいけない」と言うのです。つまり値切れ、ということです。私が買ったものだったら、300 円くらいまで値切れると言われました。買い物で値段交渉をするのはもともと慣れていませんでしたが、それを言い値の 3 割まで値切らないといけないという中国の文化にびっくりしたことを覚えています。
アブラハムは 3 割ではなく 2 割までがんばりました。神様に対してここまで交渉した人間というのはいないでしょう。これはアブラハムが父である神様を強く信頼していたからこそと言えるのではないかと思います。
ソドムの町は、正しい人として選ばれた人はアブラハムの親族であるロトの家族しかいなかったため、結局 10 人にも満たずに滅ぼされてしまいます。しかし、神様はアブラハムの信頼に応え、ロトの家族をソドムの町から導き出してくださいました。
ルターは、小教理問答書に、朝の祈り、食前の祈り、食後の祈り、夕べの祈りの中で主の祈りを捧げなさいと書いています。1 日 3 食とすれば、1 日に 8 回主の祈りをしなさいということです。これは勧めではなく「一家の主人が教えなければならない」ものだと書いています。説教の準備として小教理問答書を読み直してみましたが、この部分を読んで、一家の世帯主である私は反省しきりでした。
祈りは私たちが神様に向き合う時間です。疲れ果てて神様に向き合いたくない日もあるかもしれません。けれども神様は私たちを愛して、いつも私たちを見つめてくださっています。私たちも神様を信頼して、毎日 8 回とはいかないかもしれませんが、祈りによって神様に向き合っていきたいと思います。