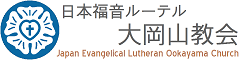十字架の賛美は止まらない
ルカによる福音書 19: 28 – 40
今日の福音書の日課は、イエス様がエルサレムに入られる、いわゆる「エルサレム入場」の場面です。私たちはこの聖書の箇所から、イエス様が大勢の人々に歓迎されながらエルサレムに入られるシーンをイメージします。しかし、それは私たちのひいき目だろうと思います。確かに弟子たちの群れは数々の奇跡を目の当たりにして、興奮気味にイエス様を迎えたかもしれません。しかし、想像するにその人数は決して多くはなかったと思います。なぜならば、もしそんなに大群衆であったならば、エルサレムを管轄していたローマの兵隊たちが黙っていたはずがないからです。大群衆が歓声を上げればすぐに兵隊たちは、ローマの支配に対する暴動と身構えたはずです。しかしその群集は多くても数十人、その中心にいるのは子ろばに乗った見栄えのしない人物だったのです。兵隊たちは城壁や砦の上から、それも見世物を見るかのように嘲笑気味に眺めていたでしょう。
しかし、彼らは知りませんでした。主をほめたたえるこの歓声の意味を。ただ民衆が大騒ぎしているようにしか考えていませんでした。民衆もまた何も知らずに上げたこの歓声が、神様の救いを示していることは知りませんでした。そして、その救いは十字架という、人々からさげすまれる処刑によって成就することなど想像だにしなかったことでしょう。
今日の福音書の日課は、不思議なことで満ち溢れています。まずイエス様は、エルサレムに入るためにろばの子を求められます。それも村に入る以前に、つないであるろばの存在を知り、そこで交わされるであろう持ち主との会話まで予言して、弟子たちにその時の応対の仕方を教えられています。普通に考えてもそれは不思議なことですが、もう一歩踏み込んで考えると、今まで歩いて旅をされて来たイエス様がゴールであるエルサレムの直前になってろばに乗ろうとされているのも不思議なことです。ベトファゲもベタニアもエルサレムから二、三キロのところにあるすぐ脇の村でした。さらにもう少し考えると、エルサレム入場を英雄の凱旋と考えるならば、ろばではなく馬のほうがふさわしかったはずです。イエス様はなぜエルサレムの直前でろばにこだわられたのでしょうか。
旧約聖書の日課は、イスラエルの救いの預言です。そこには救い主が子ろばに乗ってやってくることが預言されています。イエス様は、ご自分がエルサレムに入るということが、この預言の成就であることを強く意識されていました。すでに語ら
れている福音書をたどるならば、イエス様は既に二度エルサレムに来られています。
三度目にあたる今回は、これまでの二回とは違うのです。それは救いの成就としてのエルサレム入場なのです。
神様は高ぶりを嫌われます。ゼカリヤの預言において、高ぶりは拒否されています。イエス様が子ろばを選ばれたのも、このためです。ろばは、民衆の間では日常に用いられるものでした。一方、馬は権力者が使用するものです。支配の象徴、力の象徴です。弱い人、苦悩している人、病いの人と共に過ごしてこられたイエス様には不似合いなものでした。イザヤ書53章に示されるように「彼が担ったのはわたしたちの病、彼が負ったのはわたしたちの痛みであった。」神様がイエス様を通して示される神の支配は最初から最後まで、君臨するのではなく、傍らにおられるのです。
パウロもフィリピの信徒への手紙で次のように述べています。「キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。」
福音書の日課の続きを見てみましょう。民衆が叫ぶ賛美の声に、ファリサイ派の人が、「先生、お弟子たちを叱ってください」と言いました。イエス様を祭り上げるような民衆の振る舞いが、気に入らなかったのか、それとも大騒ぎになってローマ兵が動き出すことを心配したのかはわかりません。しかし、その言葉に対してイエス様は「言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫びだす」と答えられました。「石が叫びだす」、不可解な言葉です。この言葉をどのように受け止めればよいのでしょうか。
エルサレム周辺は、石灰岩で覆われています。もちろん緑がないわけではありません。しかしいたるところ岩が露出していますし、建物もこの岩や石で作られていました。また荒野に行けば、荒涼とした石と岩だけの風景が広がります。そこには風が吹き抜けるだけです。当然のことですが、岩や石は静寂と沈黙が支配する世界です。しかしそう考えるとかえって「石が叫びだす」という言葉の強さが伝わってきます。語るはずのないものが語り、叫ぶはずのないものが叫ぶのです。さらに言えば、救えるはずのないものが救い、救われるはずのないものが救われるのです。
「石が叫びだす」、2千年に渡って叫び続けた存在があります。それが教会です。石とはペトロです。ペトロは後の教会の礎となりました。その細かい歴史は時には政治的になり批判されるところもありますが、しかし歴史を通して教会はイエス・キリストは主であると叫び続けたのです。時には力強く、時には弱弱しく、歴史の中に消え入りそうになっても、再び復活し、信仰を伝え続けるのです。
罪人として裁かれ、十字架という残忍な方法で殺されるイエス様。そしてそれはユダヤ人にとっては屈辱的なローマ式の処刑方法です。そのような仕方で死ぬイエス様が、どうして人を救うことが出来るのでしょうか。みすぼらしく子ろばにまたがっている人が、どうして復活して死の勝利者となることが出来るのでしょうか。
十字架は神様が決められた救いの方法です。私たちが期待する仕方、私たちが予想できる仕方ではなく、神様の強い愛の表れです。もはやそれは誰にも止められません。