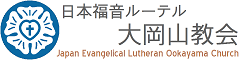いつか と いま
ルカによる福音書 23: 33 – 43
こどもが通っていた学校にはクリスマス音楽会という行事があります。これは主に受験生やその保護者に向けた行事で、その中に高一の生徒たちに40名程の有志の父親を加えた合唱があります。こどもはもう卒業していますが今年声がかかって、歌詞の解説を父親たちにすることになりました。『あめにはさかえ』(ルーテル教会では『平和の君に』)、の歌詞に『君を称えよ』という一節があります。讃美歌の歌詞というのは馴染みのない人には実はわかりにくいもので、君ってあなたのこと?王様のこと?じゃあイエス・キリストってどこの国の王さまだったの?といった具合です。ではイエス様はなぜ君=王なのでしょう?
そもそも、王とはどのような人をさすのでしょう?王は立法・司法・行政あらゆる権力全てを一人で掌握する人で、強い発信力によって国民に影響力を持つ存在です。更にイエス様の時代・古代オリエントの王になりますと、神の代理としてこの世を統治する一元的で神権的な支配者で神と人間を結ぶ存在でもありました。王は国を治め、宗教的、政治的、軍事的な最高権力を持ち、社会と国民を治めます。つまり、イエス様が王であるということは、イエス様は神様に代わって国と民を支配するということです。
もう少し具体的に、イエス様がどのような王様なのかを考えてみたいと思います。キリスト=救い主は当時のユダヤの人々に切実に待たれていました。イエス様の時代はご存知の通りローマ帝国の統治下にありました。帝国支配下のユダヤの人々は救い主を待っていました。そもそも救い主を求める考えは預言者イザヤの時代に始まり、バビロン捕囚時代にピークを迎えます。異教の外国人による武力や経済力=「物」による支配、帝国の王が神のように振る舞う支配=「心」の支配からの解放と本当の神様による正当な支配をユダヤ人は求めていました。これはイエス様の時代でも同じでした。
しかしイエス様はメシアであり王様ですが、待たれていたこのような王様とは違いました。ご存知の通りイエス様はイスラエルを率いて戦い超大国を追い払う王ではありませんでした。ではイエス様は私たちを何の支配から救ってくださるのでしょう?
私たちは罪に支配されています。神様ではなく自分自身を中心に据えようとする心、このような心を聖書は罪と呼びます。人間は自分の力ではどうしようもできない不幸、意味理不尽な事故・災害・不運に対して『何が悪くてこのようなことが起きてしまったのだ?』という呵責(かしゃく)の念にしばしば苦しめられます。この呵責は“人間は自分の周りの全てを掌握し自分でコントロールできる”、そのような思い込みの裏返しです。自分の世界は全て自分で動かすことができると思い込む心こそ罪です。私たちはその罪に支配されています。その支配からは自力では抜け出すことができません。イエス様は私たちをそのような罪の支配から解放し、神の国に迎え入れることによって、自由を与えてくださいます。その神の国の王はイエス・キリストです。イエス・キリストの支配が全てに及ぶとき、終末の救いは完成します。
でも実際の王の姿、今日の福音書の日課ではイエス様は十字架に架けられています。その姿は無力です。十字架にはその様子に対し皮肉を込めて看板が掲げられます。『これはユダヤ人の王』。イエス様を十字架に付けたローマの兵士や一緒に十字架にかけられた受刑者からは馬鹿にされます。『お前が王なら、救い主なら、十字架から自力で降りて来い』。このイエス様の姿は、神様の望みに従い、私たち人間の救いのために進んで自らの命を捧げる姿です。これがキリストの王としての姿です。人間の目には圧倒的な敗北にしか見えない十字架、これはイエス様が全ての者に仕える王であることを示します。十字架はイエス・キリストがこの世には属さない神の国の王であることを示しています。
イエス様と一緒に十字架にかけられたうちの一人の受刑者はイエス様を馬鹿にした受刑者に言います。『お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は、自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。』彼はイエス様に乞います。『イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください』彼は自分の犯した罪とイエス様が神からの救い主“王”であることを告白します。『今ここで十字架から降ろしてくれとは言いません。いつか天の国であなたが王になる時、わたしを思い出してください。それだけで結構です。』
この時、彼の思いは遠い将来“いつか”でした。今はもう仕方ない、でもいつかわたしを顧みて(かえりみて)ください。イエス様は答えます。『あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる』“今日・いますぐ”です。十字架に架かり、息も絶え絶えの男に『あなたも私もいま楽園にいる』と言われて説得力はあるでしょうか?
ヨハネによる福音書に『ラザロの復活』という物語があります。マルタとマリヤというイエス様と懇意にしていた姉妹の兄弟・ラザロが病気で危篤になりました。イエス様に治してもらうために二人は使いをイエス様の元に送りましたが、イエス様が着いたときにはラザロはもう亡くなっていました。間に合わなかったイエス様は『あなたの兄弟は復活する』と出迎えたマルタに言います。それに対して無念さを隠しながらマルタは『終わりの日の復活の時に復活することは存じております。』と答えます。『はい、あなたの言う通りラザロは復活します。私は信じます。でもそれはいつか先の話・終末のことで、もうラザロは死んでしまいました。』
マルタはイエス様を信じていました。でも終わりの日はまだ先、希望もまだ遠く、いつかは果たされるけれど…というものだったと思います。そのようなマルタにイエス様は心を激しく動かし、墓の中のラザロを復活させました。正確に言いますとラザロの復活は肉体の蘇生であり、キリストの復活による永遠の命ではありませんのでいつかはその生涯を終える時が来ます。しかし、このラザロの復活は神の国・天の国はまだ見えないが確かに来るという確信を与えます。この確信は今を生きる者に希望を与えます。十字架の上でイエス様に願った男もその瞬間に『今日楽園にいる・今一緒に神の国にいる』と言う言葉によって与えられる希望、人間の時間の尺度を飛び越えて与えられる終末の希望に包まれたのだと思います。
見えないものを信じる信仰を強く持ちなさい、見えないのは信仰が足りないとは言いません。見えないけれど希望となり喜びとなるものが備えられていることを覚えましょう。これはまだ何も始まっていない、まだ生まれたばかりの救い主を見て、その先にある救い・平安・神の国を喜ぶクリスマスの心に通じるものだと思います。