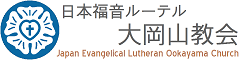招きとへりくだり
ルカによる福音書 14: 1, 7 – 14
本日与えられた聖書箇所は、イエス様が上席を選ぼうとする人々に気づいて話されたたとえが中心となっています。14 章 1 節には「イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになった」とあるため、このたとえが話された場もまたファリサイ派の議員の家の中であると考えられます。イエス様が話されたたとえは次のようなものです。「婚宴に招待されたら、上席に着いてはならない。(中略)招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、『さあ、もっと上席に進んでください』と言うだろう。そのときは、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」このたとえを、私たちはどう聴いていけばよいのでしょうか。
上席を選ぼうとするということは、いったいどのようなことなのでしょうか。実はギリシャ語における「上席」という言葉は、「食卓における最上座、主人の隣」という意味を含んでいます。ここから、いくつかのことが思い浮かびます。まず一つ目が、ゼベダイの子ヤコブとヨハネの言葉です。「栄光をお受けになるとき、わたしどもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。」(マルコ 10:37)彼らはイエス様の隣、つまり最上座を求めたのです。またヤコブとヨハネだけでなく、弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いかを議論している場面も聖書には記載されています。「弟子たちの間で、自分たちのうち誰がいちばん偉いかという議論が起きた。」(ルカ 9:46)そして二つ目がこのたとえが語られた場にいるファリサイ派の人々についてです。ルカ福音書 14 章では上席を選ぼうとしていた人々がファリサイ派の人であるとは断定されていません。しかし同じくルカによる福音書 11 章には、イエス様がファリサイ派の人から食事の招待を受けてその家に入るという 14 章と同じような場面設定の中で、彼らが上席を選ぼうと固執していることについてイエス様が言及されています。「あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。会堂では上席に着くこと、広場では挨拶されることを好むからだ。」(ルカ 11:43)このことから、今回の聖書箇所で上席を選ぼうとしている人々もまたファリサイ派の人々であったのではないかと推測することができます。
イエス様の弟子たちとファリサイ派の人々に共通していることはいったい何でしょうか。
それは、自分は上席に相応しいものであるという考え方です。自分の価値や栄誉を高め、自分がその席に座るに値するものとなることを追い求めていたのです。特にファリサイ派の人々や律法学者は律法を遵守し、神の掟に従う生き方を人々に説いていました。己がより神に相応しいものとなることを彼らは追い求めていたのです。
このことは、現代を生きる私たちにも当てはまります。現代を表す言葉の一つに「自己実現」が挙げられます。私たちは子どもたちに対して、「大きくなったら何になりたい?」と聞きます。子どもたちは幼い頃から、この言葉を繰り返し聞いて生きていきます。夢や目標は人生を生きていく中で大切なものです。しかしそのような夢や目標をかなえること、自分の価値を高め自分らしく生きるという自己実現こそが人生の目的であるのだという考え方が現代には存在しています。また教会の中であっても同じです。信仰生活の中で「あの人はクリスチャンに相応しい言動、生活ができていないのではないか。」と考えたことはないでしょうか。逆に、「私はクリスチャンに相応しくない。そのような価値は私の内にはない。」と考えてしまった経験はないでしょうか。これらのような思いを一度も抱かずに生きていくことは、おそらく不可能なのではないかと思います。クリスチャンに相応しい、神の民として相応しい生き方を追い求めたいという教会の中の「自己実現」は、2000 年前から現代にいたるまで変わらず私たちの内に存在しているのです。
しかしそんな私たちに聖書は語りかけます。今回のたとえではへりくだることに焦点が当てられています。「へりくだり」とはいったい何でしょうか。「へりくだり」は「謙虚」とは異なります。謙虚とは自分を下にして相手を敬うことです。特に日本では謙虚は美徳の一つとして考えられてきました。しかしそのような謙虚さ、美徳が私たちに求められているのではありません。私たちに求められているのは「へりくだり」です。へりくだるとは、自分がまことに神にふさわしいものではないことを知るということです。己が神からの招きにふさわしくない、それに値しないものであるということを受け入れるということなのです。しかし神様はそんな私たちを招いてくださっているのです。
今回の聖書箇所では「席」という言葉が繰り返し用いられているためそちらに意識が向けられがちですが、ギリシャ語では別の言葉が繰り返し用いられています。それは日本語では「招待」や「招き」と訳されているギリシャ語で、今回の箇所だけで 8 回も用いられています。このギリシャ語は「呼ぶ、招く、召し出す」といった意味を持っています。つまり、「招き」もまた今回の主題の一つとなっているのです。
聖書箇所の後半では招くことについて語られています。そこには「貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。」と記されています。これらの人々には、当時のイスラエルでは神殿に入ることができなかったという共通点があります。当時のイスラエル、特にサドカイ派と言われる人々は、神殿こそが礼拝の中心であると考えていました。つまりここに記されている人々は神の礼拝、神からの招きに相応しくないと考えられていたということです。しかしイエス様はそのような人々のもとを訪れました。神に相応しくないと考えられていた人々のもとを、神自らが訪ねてくださったのです。では、現代において神に相応しくないと考えられている人々はいったいどのような人でしょうか。
ルターは雷に打たれる恐怖から修道士になることを誓願し、司法科の歩みを離れて修道士となりました。修道士になってからのルターは模範的な修道生活を送り続けていました。しかしルターの心が休まることはありませんでした。どれだけ模範的な生活を送ろうとも、自分が神に認められたと思うことはできなかったのです。そして後にルターは気づかされました。自分の努力や功績によっては、神に相応しいものとして認められる義は得られないということを。 ルターの説いた義認論とは、神に義と認められるような、神に相応しい人間はこの世に一人もいないということです。しかし神はイエスという一人の人間となって、十字架につけられるという人間の常識をはるかに超えた方法を選ばれました。神がこの世に来られ、自らがへりくだられたのです。「キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わずかえって自分を無にして僕の形をとり人間と同じ者になられました。人間の姿で現れへりくだって、死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でした。」(フィリピ 2:6-8)この十字架の死という神のへりくだりにより、私たちは罪あるもの、神の義に相応しくないものであるにもかかわらず、義と認められるのです。私たちは本来、神に相応しいものではないのです。しかしそうであるにもかかわらず、神によって義と認められているからこそ恵みなのです。自分がまことに神にふさわしいものではないということを知ること。そこにこそ私たちの喜びの根拠があるのです。
聖書箇所で言われているお返しすることができない人たち。それは神に相応しくない私たちに他なりません。私たちに与えられているこのプレゼントに対して、私たちがお返しできるものは何ひとつありません。できることはこのプレゼントを感謝して受取ることだけです。カール・バルトは「Yes こそがキリスト者の生活の全てである」と言いました。それは、本来 No と言われるべき私たちを神様は受け入れ、私たちに対して Yes と語り掛けてくださっているということです。そしてこの神様からの Yes に対して、私たちが Yes と答えて生きていくということなのです。
神様は罪深く、自分の行いや自分の価値を誇ろうとしてしまう私たちにへりくだるように語り掛けておられます。それは反省しなさいということや自分を卑下しなさいということではありません。自分がまことに神にふさわしいものではないにも関わらず、神様が招いてくださっているというこの恵みに目を向けなさいということです。弟子たちは自分たちの偉さを競い、ファリサイ派の人々は自分たちが上席に着くことにこだわっていました。そのような自分の義を追い求めるような生き方はこの神様からの恵みを見失ってしまう生き方です。そこから立ち帰りなさいと、私からの招きと恵みを見なさいと聖書は語り掛けているのです。
最後にこの礼拝ののち、私たちはこの世と隣人に対して派遣されていきます。今日の聖書箇所はお返しすることのできない人々を招くようにと記されています。お返しすることのできない人々とは誰でしょうか。それは先ほどにもあったように、私たちすべての人間です。つまり、まだ教会に連なっていない方、私たちと共にこの世を生きている隣人たちをも招くようにと聖書は語り掛けているのです。成果主義や自己実現に捕らわれている人々、それによって自らを見失いそうになっている人々、自分は神にふさわしくないという思いに捕らわれている人々に対して、私たちはそのような生き方から自由にされたものとして遣わされていくのです。へりくだり、神からの招きに Yes と答えた私たちは、この恵みを伝えるためにこの世に派遣され仕えていくのです。そしてそのような歩みは、己がまことに神に相応しいものではないというへりくだりによってこそなすことができるものです。神に相応しくない私たちを神様が受け入れ、私たちを招いてくださっているというこの恵みの喜びに満たされつつ、今週もまたこの世に遣わされ、歩んで参りましょう。