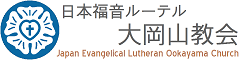神様は待っておられる
ルカによる福音書 15: 1 – 3, 11b – 32
私たちは自由を求めます。仕事に追われ時間に追われていると、特にそれらから解放されたいと願います。
自由とはいったい何なのでしょうか。自由には何が必要なのでしょうか。私たちはまず時間やお金のことを考えます。時間があってもお金がないと身動きとれないからです。しかしそれが自由を保障するのでしょうか。確かに私たちは様々なしがらみ、制約の中で生活していますが、それがなくなったから満足できる自由を手にすることが出来るかというとそうではないように思います。
今日の福音書の日課は、大変有名な「放蕩息子」の譬です。これは15章にある「見失った羊」の譬と「失くした銀貨」の譬と並んで、いわば失われたものが見つけ出された喜びを伝える譬の三部作です。この譬に「放蕩息子」とついていますので、実際に放蕩に身を崩した弟のほうに焦点が当てられますが、兄もまた弟が父親から自由になりたいと願っているのと同じように、兄もまた自由を求めていると思うからです。
弟が父親に「わたしがいただくことになっている財産の分け前をください」と願い出ます。当時のユダヤ社会では、後に家長となる長男の権威がつよく、次男はやがては家を出るか、長男のもとで暮らすことになっていました。弟はどうせそうなるのであれば早く家を飛び出して自由に暮らしたいと思ったのです。何日もたたないうちに弟は財産を全部金に換えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄に使い果たします。彼が放蕩の限りを尽くしたのは、遠い国で自由に生きたかったからです。律法やユダヤ教の習慣、さまざまな束縛から自由になりたかったのです。
芥川龍之介の「杜子春」を思い出します。もともとは金持ち、しかし今はお金もない、仕事もない。そんな杜子春が老人と出会う。彼は影の頭の部分を掘ってみるように言う。金銀が埋まっていた。金持ちになり人が寄ってくる。しかし貧乏になると、人は誰も声をかけない。また老人と出会う。老人は胸のあたりを掘るように言う。再び金持ちになる。また人が寄ってくるが、お金がなくなると人は去っていく。また老人に出会う。老人は腹のあたりを掘るように言う。しかし杜子春はもういいと言って断る。さすがの杜子春も人間の欲深さと現金さに愛想を尽かすのです。物語はまだ続きますが割愛します。
放蕩息子のところにもお金があるうちは人が寄ってきます。ちやほやもてはやします。しかしいったんお金がないとわかると、薄っぺらい人間関係は崩れてしまいます。利用価値がないと捨てられてしまうのです。悪いことにそんなときその地方では飢饉が起こります。人々は自分の食いぶちで精いっぱいです。誰も弟に目を向ける人などいません。ある人のところに身を寄せますが、その人は彼に豚の世話をさせるのです。ユダヤ人にとって豚は宗教的に敬遠される動物です。豚の世話をするということは異邦人のすることです。しかしもはや彼にとってそれをえり好みすることはできません。それどころか豚の餌であるいなご豆を食べて腹を満たしたいと思うほどでした。自由を求めて家を飛び出した彼でしたが、一文無しになってもっと不自由な生活を余儀なくされていたのです。そんなとき彼は自分の家を思い出します。『父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどパンがあるのに、わたしはここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」と。』
虫がよすぎる、甘えていると言われればそれまでです。むしろ彼には帰る場所があった、頼る父がいただけよかったと言えるかもしれません。彼は父親のいる家に帰るのです。家に帰ると、彼がまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻するのです。遠く離れている息子を見つけるということは、父が、息子が帰ってくることを今か今かと待っていたことにほかなりません。息子は考えた通りのことを言いました。しかし父親は息子が言い終わる前に、僕たちに『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』と言って、祝宴を始めたのです。父親にとってどれだけ大きな喜びであったかがわかります。
そのころ兄は畑で仕事をしていました。家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえたので、僕を呼んで「一体これは何事か」と尋ねます。僕は。『弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を屠られたのです。』これを聞いた兄は怒りのあまり家に入ることができませんでした。家の仕事を捨て、家族の責任を捨て、勝手に財産を持って出て行った者が、のこのこ帰ってきたのです。自分はと言うと、長男の責任を果たすために働き、律法はもちろん様々な習慣を忠実に守ってきたのです。彼自身が父親に訴えているように「わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度も」なかったのです。彼が腹を立てるのももっともなことでした。しかし父親は言います。『子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。』」
兄は朝から晩まで父親と共に働き、父親と一緒に暮らしていました。しかし実は彼もまた弟と同じように、父親から自由になりたいと願っていたのです。心で願うということはすでに父親から離れているのと同じです。しかし、本当の自由は父親から離れることではありませんでした。弟が実際に経験したように、一見自由と思われる生活も父親から離れての生活は不自由な生活なのです。言うまでもなく、この父親は神様のことです。神様から離れることが自由をもたらすのではなく、神様と深い結びつきの中にあることによって真の自由が与えられるのです。創世記の3章には人間が罪を犯す「堕罪物語」が書かれています。蛇が女を誘惑し「それを食べると、目が開け、神のように善悪を知る者となる」と言います。そそのかされて男もまたその実を食べます。そうすると彼らは自分たちが裸であることを知り、いちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとします。それだけではありません。神様が「どこにいるのか」と探されると、彼は「あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり、隠れております」というのです。善悪を知り、自由を手に入れるはずが、神様を恐れて生きなければならなくなったのであり、神様と等しくなるはずが、神様から離れて生きなければならなくなったのです。
わたしたちはこの二人の兄弟に私たち自身の姿を見ることができます。具体的にみ言葉から離れて生きているのか、それともみ言葉近く生きていながらも心が離れてしまっているか。あるいはその中間か。弟の姿にしろ、兄の姿にしろ、いったん離れてしまった私たちを、父である神様は、いつも待っておられるのです。その姿は、最初のたとえにあるように、迷子になった羊を探し求める羊飼いのように探し求められるのです。そして神様のみ腕の中に立ち返るならば、神様はすべてをゆるし、わたしたちを受け入れ、喜んで下さるのです。この喜びは、ただの歓迎の喜び、再会の喜びではありません。復活の喜びです。「死んでいたのに生き返った」との父の言葉通り、神様を離れていることを聖書は死んでいるのと同じように考えるのです。しかし、神様に立ち返る時、わたしたちは生きた者となるのです。よして真の自由を手に入れるのです。これが天上における最大の喜びです。
父なる神様はその深い愛のみ腕を広げ、わたしたちを待っていてくださいます。わたしたちはこのみ腕にためらうことなく飛び込もうではありませんか。